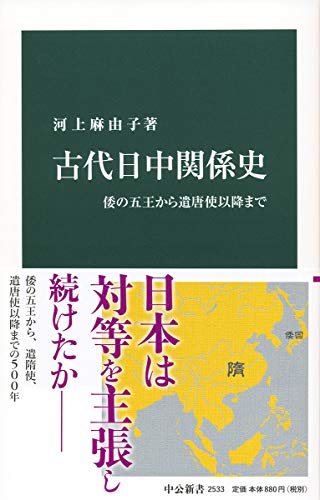イヴォ・ヴァン・ホーヴェ演出、ITAの『ローマ悲劇』を配信で見た。新型コロナがなければ来日していたはずの演目である。2007年に作られた作品で、シェイクスピアの『コリオレイナス』、『ジュリアス・シーザー』、『アントニーとクレオパトラ』をまとめて6時間に編集したものである。先月のKings of Warに続いて大変な長丁場だ。
ita.nl
家具が置いてある大きなセットが舞台で、衣装などは完全に現代である。ふだんは観客がいろんなところを動けるらしい。今回は観客が入れないので、そのかわりにカメラをいろいろ動かしており、カメラワークは舞台の撮影としてはほとんど完璧といっていいような洗練度である。休憩時間もカメラが回しっぱなしで、ナレーターというかテレビ局のブロードキャスターみたいなMC(Noraly Beyer)が休憩中に「あと何分でシーザーが死亡します」みたいなことを説明してくれる。テロップでも「シーザー死亡まで3分」などの情報が出るようになっている。死ぬ描写はほぼ血などが出ないシュールでちょっとブラックユーモア的なもので、真ん中のデッドゾーンみたいなところに運ばれると死亡宣告となる。
序盤は大変面白く、90分でコンパクトに仕上げた『コリオレイナス』といい、驚くほどいけすかない政治家風なブルータス(Roeland Fernhout)と扇動がものすごく得意なアントニー(Hans Kesting)の対比がはっきりした『ジュリアス・シーザー』といい、非常にシャープな政治劇である。最初はコリオレイナス(Gijs Scholten van Aschat)の母という私的な立場であるにもかかわらず強い政治家として力を振るうヴォラムニア(Frieda Pittoors)が存在していて政治領域における公私がはっきりしていなかったローマが、『ジュリアス・シーザー』の時代になるとシーザー(Hugo Koolschijn)の妻キャルパーニア(Janni Goslinga)やブルータスの妻ポーシャ(Ilke Paddenburg)がほぼ力を持たなくなって公私の別がはっきりするようになり、一方で公的な女性政治家としてキャシアス(Marieke Heebink)やオクテーヴィアス(Maria Kraakman)が登場するようになる(このふたりは男性から女性に変更されている)。『アントニーとクレオパトラ』では、アントニーとクレオパトラ(Chris Nietvelt)の関係はもちろん、オクテーヴィアスがオクテーヴィア(Ilke Paddenburg)をアントニーと結婚させるなど、再び政治領域における公私の別が曖昧になる。
『ジュリアス・シーザー』あたりまでは、けっこうひとりひとりのキャラが不愉快な人にせよ面白い人にせよけっこうはっきりしていてメリハリがある。とくに『ジュリアス・シーザー』では、通常のプロダクションでは、全く融通のきかない真面目ちゃんかもしれないがとにかく善良で誠実であることにかけては折り紙付きの人物として演じられることの多いブルータスが、わりと既得権益を生かして活動していそうな政治家になっており、かなり斬新だ。シーザー暗殺後にブルータスがあらかじめ用意していた紙を見ながら演説をするあたり、どう見ても政治パフォーマンスとしてはイメージが悪い。一方でアントニーはブルータスのあまりにもそつが無くてむしろ人間味のないスピーチを見て、用意してきた原稿を捨てて涙ながらにマイクとカメラに向かって訴える感情の政治を行う。このあたりの描き分けは実に見事だ。衣装を使った表現もしっかりしていて、ブルータスはかなり隙の無い格好をしているのだが、アントニーは演説の前にわざとネクタイを緩めるなど、人から親近感を持ってもらえそうな着崩しを行う。またキャシアスは高いヒールの靴に胸の谷間が見えるタンクトップをビジネススーツにあわせたけっこうゴージャスな中年の女性政治家である一方、オクテーヴィアスは露出度の少ないスーツで髪型や靴ももうちょっと実用的で堅い感じにそろえているなど、性格の違いが衣装からわかるようになっている。
しかしながら、私はここまでのシャープで醒めたトーンからして『アントニーとクレオパトラ』は悪い予感がするな…と思っていたのだが、それは完全にあたってしまった。もともとイヴォ・ヴァン・ホーヴェはフツーに情熱的でセクシーな男女関係を描くのはけっこう苦手だと思うのだが(『ブロークバック・マウンテン』は映画ほどではないにせよわりとちゃんと恋愛ものだったので、男同士だとできるのかも)、『アントニーとクレオパトラ』は主役二人の間にあるセクシーなテンションが華やかに描けていないせいで、かなりダラダラしてうるさいだけになっているところがある。ここだけで150分くらいあるのだが、カットの仕方が悪いのか、アントニーもクレオパトラもあまり政治家らしく見えず、昔はキレがあった人たちが年とって無能になったみたいな印象を受けてしまう。いきなりアントニーがパンツ一丁で出てくるなど露出度が高い描写や性的描写はあるのだが、それが全然お色気につながっていなくて、なんとなく不穏でイヤな感じがするだけである。女性が多いエジプトのクレオパトラの宮廷は騒々しくてあまり魅力がない一方、オクテーヴィアスはオクテーヴィアをいじめる一方でキスするなど近親相姦的な関係で、全体的に女性同士のつきあい方が見ていてものすごく居心地が悪い一方、男性陣はあんまり賢く見えない。これはちょっとミソジニー的にすら見えると思った。イノバーバス(Bart Slegers)はけっこう良く、外に飛び出して暴れて死んでしまうところはものすごくエネルギッシュで面白かったのだが(全くマスクをしていない人たちの間に突っ込んでいって触ったりするので最初は録画かと思ったのだが、ライヴらしい)、他にあんまり見せ場がない。終盤はもっとキレとメリハリが要ると思う。